六曜(ろくよう、りくよう)は、暦注の一つで、六曜により、その日の吉兆を占うものとされています。
先勝(せんしょう、せんかち)・友引(ともびき)・先負(せんぶ、せんぷ、さきまけ、せんまけ)・仏滅(ぶつめつ)・大安(たいあん)・赤口(しゃっこう、しゃっく)の6種の曜があります。
六曜は「先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口」の順で基本的に繰り返されます。
旧暦の各月の1日を基準日として、六曜が定められています。
例えば、先勝の基準日は、旧暦の1月1日と7月1日で、
旧暦1月1日 先勝
→旧暦1月2日 友引
→旧暦1月3日 先負
→旧暦1月4日 仏滅
→旧暦1月5日 大安
→旧暦1月6日 赤口
→旧暦1月7日 先勝
→ ・・・ と繰り返されます
先勝(せんしょう、せんかち)
先勝は、「せんしょう」「せんかち」と読みます。
「先勝」は、「先手必勝」の意味。「先んずれば勝つ」という意味を表した日です。
言葉の意味合いから縁起の良さそうな日に思われますが、何事も早めに済ませることが重要で、良い運勢は午前中のみとなります。
急ぐことは吉。午前中は吉、午後は凶。
基準日:旧暦の1月1日、7月1日 が先勝
友引(ともびき)
「友引」は「ともびき」と読みます。
「友引」は、「友を引く」の意味。「勝負がつかず引き分ける」という意味を表した日です。
「友を引きこむ」ということから、祝い事・慶事は良いが、葬式などの弔辞・凶事は不向きとされています。
朝夕は吉、正午は凶。
基準日:旧暦の2月1日、8月1日 が友引
先負(せんぶ、せんぷ、さきまけ、せんまけ)
「先負」は「せんぶ」と読み、「せんぷ」「さきまけ」「せんまけ」と読まれることもあります。
「先負」は、「先勝」の逆。「先んずれば負ける」の意味。慌てず、焦らず、平静さを保って行動すること。
「負」という文字が入っていますが、縁起が悪いわけではなく、午後になると吉となります。
午前中は縁起が悪いとされていますので、午後から行動するのが良く、急用や争いごとは避けたほうが良い。
午前は凶、午後は吉。
基準日:旧暦の3月1日、9月1日 が先負
仏滅(ぶつめつ)
「仏滅」は「ぶつめつ」と読みます。
「仏滅」は六曜の中で最も凶日とされる日です。「仏も滅する悪日」という意味。
元々「物滅」と表記されていたのが、仏滅に変化したといわれています。「物滅」は「すべてが空しい」という意味で、物事が終わりを迎える日という意味があります。また、「(物が滅びて)すべてが新しく始まる日」という考え方もあり、仏滅の日に葬式を行うことは、悪縁を断ち切り新たな人生のスタートを切ると捉えることもできます。
祝い事・慶事は不向き。葬式などの弔辞・凶事はよい。
万事に凶とする大悪日
基準日:旧暦の4月1日、10月1日 が仏滅
大安(たいあん)
「大安」は「たいあん」と読みます。
「大安」とは、六曜の中で、最も幸運で縁起の良い日とされる吉日です。「大いに安し」という意味。
あらゆる物事において、良いとされ「大安吉日」と呼ばれることもあります。一日中縁起が良く、どんなことも積極的に進めてよく、とりわけ結婚式に最も適している。
大安の日に適した行事
・結婚式や入籍、結納などのお祝いごと
・開業や開店、登記、建築の着工日
・オフィスの移転
・婚姻届提出
万事に吉
基準日:旧暦の5月1日、11月1日 が大安
赤口(しゃっこう、しゃっく、せきぐち)
「赤口」は「しゃっこう」と読み、「しゃっく」「せきぐち」などの読み方もあります。
「赤口」は、縁起を占う際に使われる日柄です。一般的には不吉な日と考えられており、勝負事は仏滅の次に避けた方がよいとされており、婚礼行事や引っ越し、納車などは避けた方がよいとされています。
赤口の由来は、陰陽道で「赤舌神(しゃくぜつしん)」という鬼神が支配する日とされています。赤舌神は、人々や生き物を苦しめる極悪の神とされています。
「赤」という字のイメージから、火や刃物の取り扱いに注意するようにという意味もあります。
午前11時頃から午後1時頃までの時間帯(正午の前後)は吉。それ以外の時間帯は凶。
基準日:旧暦の6月1日、12月1日 が赤口
外部リンク
六曜カレンダーは、便利.comで確認できます
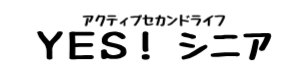

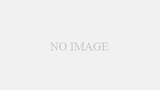
コメント